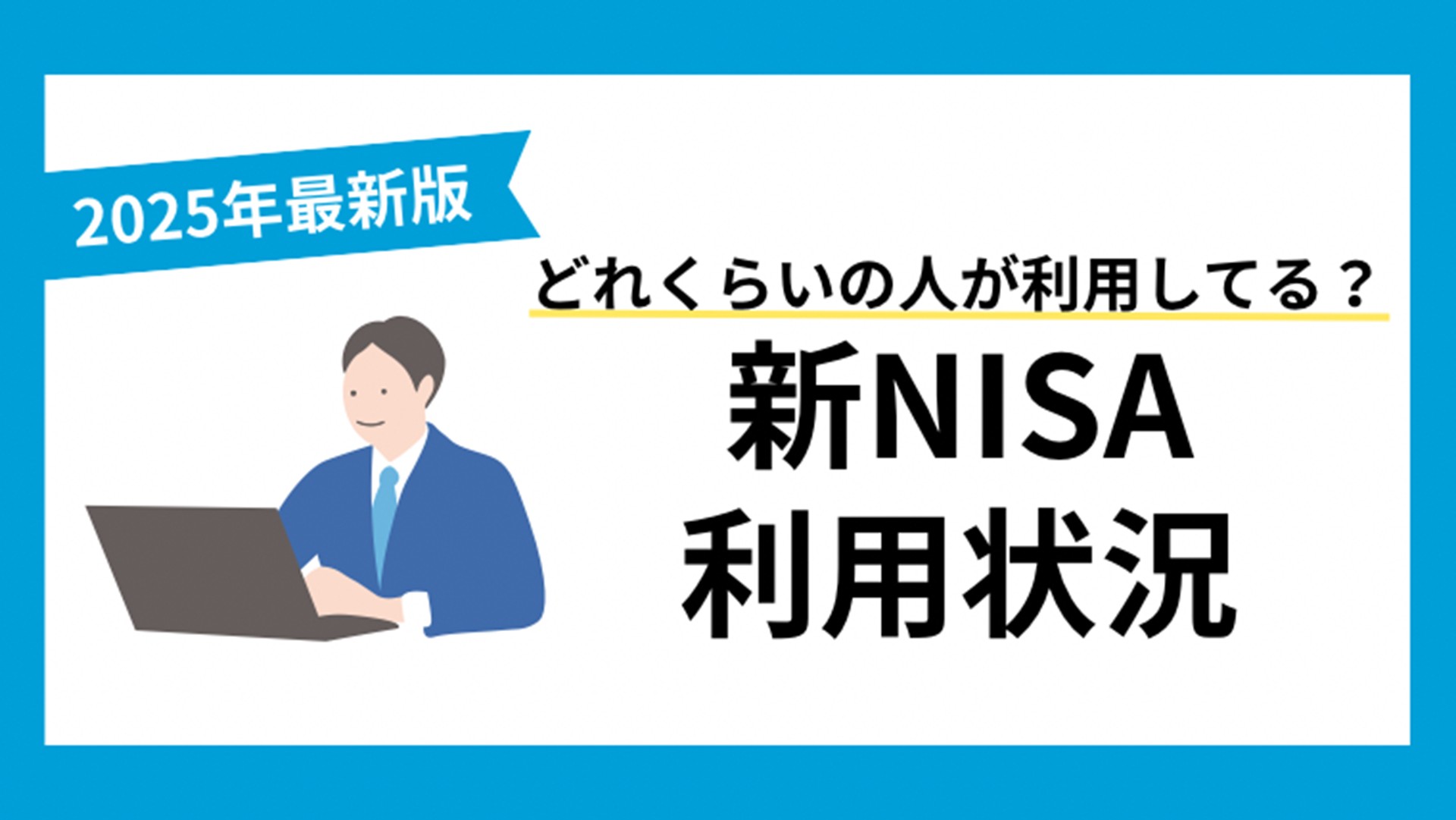NISAの改正案を徹底解説!

.jpg)
どうも、信託太郎です
お金のことならお任せあれ、信託太郎です。
2024年から導入されたNISA制度ですが、巷では神アップデートするかも!?とうわさされていますよね。
今回はその「最新版NISAの改正案」について徹底解説します。
改正案の3つの柱
具体的には、以下の3つの柱がクローズアップされています。
①こども NISA(こども支援 NISA)導入
②対象商品の拡充
③スイッチング導入(運用商品の入れ替え可能化)
.jpg)
中でも③スイッチング導入が実現されるとなると、使い方によっては従来のNISAの不自由部分が解消される可能性があります。
それでは、各改正案について見ていきましょう!
①こども NISA(こども支援 NISA)の導入
背景・現状の課題
- これまで日本には「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」があったが、2023年末で新規買付は停止されていた。
- ジュニアNISAには「18歳になるまで原則払い出し不可」といった制約があり、利便性や普及性に課題が指摘されていた。
- こうしたギャップを埋め、0歳~未成年期間からの資産形成を支援する制度として、こども支援 NISA(仮称/こども NISA)が制度改正要望の中で検討されている。
改正案の内容
制度改正要望における「こども支援措置」に関して、主に以下のような方向性が打ち出されています。
| 項目 | 要望されている内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 未成年でもつみたて投資枠を使えるよう、年齢制限を引き下げ(0 歳から可能とする案など) |
| 非課税枠 | つみたて投資枠を中心とした枠組み。年間非課税投資枠として 120 万円程度を想定する案も挙げられている |
| 保有期間・非課税継続 | 保有期間無期限または長期保有を認める方向。引き出し(払出し)制限の緩和も議論中 |
| 払い出し(出金)制約 | ジュニアNISAのような「払い出し禁止」制約を見直す案。必要に応じて途中引き出しを可能にするなどの利便性確保が要望されている |
意義・メリット
- 早期の資産形成/複利効果:幼少期から長期にわたる資産形成を可能にすれば、時間を味方に複利効果を最大化できる。
- 教育資金の準備:大学入学など将来の教育費用準備の手段として活用できる。
- 意識づくり・金融教育との連携:子どもの頃から「投資・資産形成」に親しむ機会を持てるようになる。
リスク・注意点
制度詳細(口座管理、引き出し制限、贈与税扱い、口座開設の手間など)が未確定であり、実運用上の制約がどうなるか注意が必要。
子どもの名義口座であることから、契約者・代理人の責任問題、成年後の制度移行(ロールオーバー等)の扱いなどの整理が必要。
こどもNISAの活用には、日々の固定費をいかに抑えるかがポイントになります。
↓↓詳しくは私のブログで徹底解説しているのでご覧いただき、お役立てください。
固定費についてコレだけは知っておいてください!|信託太郎の研究室
②対象商品の拡充
背景・現状の制約
- NISA/新 NISA では、対象となる金融商品の種類や要件が一定の制限を受けている。
- さらに、つみたて投資枠に入る投信は「低コストインデックス型」など基準が定められており、選べる商品が絞られている。
- 投資ニーズが多様化しており、債券ファンド、バランス型、テーマ型 ETF、リート、ESG 指向商品、さらには暗号資産対応商品(ETF 等)などを含められないか、という拡充要望がある。
改正案(要望レベル)の内容
- 税制改正要望では、「NISA 対象商品の拡充」を制度強化の要点に掲げている。
- 有識者会議の中間まとめ案では、つみたて投資枠に債券型ファンドを追加する可能性などが示唆されている。
- また、毎月分配型投信や高齢者向け商品(プラチナ NISA ブランド)への導入も要望に含まれているとの報道もある。
意義・メリット
- 投資選択肢の多様化:投資家は自分のリスク許容度や投資テーマに応じて、より自由に運用商品を選べるようになる。
- ニッチなニーズへの対応:たとえば安定性を重視した債券商品の欲求、ESG・環境関連・インパクト投資への志向などを制度内で取り込める可能性あり。
- 制度利用の魅力向上:商品選択肢が多いほど、NISA を使おうという誘因が強まり、結果として利用者の拡大が見込まれる可能性がある。
リスク・注意点
- 拡充しすぎると、初心者の迷いを生んだり、投資家の投機行動を助長してしまう可能性あり。
- 対象拡充後の規制や要件設計(信託報酬上限・情報開示義務・リスク開示義務など)の整備が肝要。
- 税制との整合性、リスク監視、過度な売買誘導を抑制するガバナンスも必要。
③スイッチングの導入
背景・現状の制約
- 現在の NISA/新 NISA制度では、口座内で保有投資商品の「入れ替え(スイッチング)」を柔軟に行うことができない。売却した場合、その分の非課税投資枠は 同年内には復活せず、翌年以降にしか回復できない制度である。
- すでに売却して枠を使っていれば、当年中に買い直すことができず、資産の見直しをしにくいという欠点あり。
- 新制度(2024 年以降の新 NISA)では、売却した分の簿価に相当する非課税枠を翌年に復活させる「再利用」制度は導入されているが、「同年中の復活」までは認められていない。(iDeCoではスイッチングが可能)
改正案(要望レベル)の内容
- 税制改正要望では、「非課税保有限度額の当年中復活(簿価相当額)」をもって、スイッチングをしやすくする制度改正が掲げられている。
- 要望の中では、「売却した資産の簿価相当額を即時に復活させ、同年中に別の商品購入に使えるようにする」仕組みを想定している。
意義・メリット
- タイミングを逃さない資産組み替え:たとえば株式が上昇した後に別のテーマ株や安定資産に乗り換える際、非課税枠を無駄にせず柔軟に対応できる。
- ライフステージ変化への対応:結婚・出産・住宅購入・子どもの教育資金など、人生イベントに応じてポートフォリオを見直しやすくなる。
- 初心者・投資改善志向者に安心:最初の選択ミスやリスクが変わった段階で、最適な配分に修正できる自由度が高まる。
- 制度効率:非課税枠を無駄に消費しない仕組みにすることができる。
リスク・注意点
- 同年中の復活を認めると、短期売買を誘発するリスク(制度を使った売買頻度増加)への警戒が必要。
- 頻繁に売買すると、手数料・信託報酬・売買コストがかかり、制度恩恵が薄れる可能性あり。
改正のスケジュール
・2025 年 8 月 29 日、金融庁は令和 8 年度(2026 年度)税制改正要望において、NISA に関する制度充実(対象商品の拡充、こども支援措置、当年中の非課税枠復活等)を掲げている。ただし「要望」段階であり、これがそのまま法律・制度化されるかどうかは国会・関連法案での調整次第である。
・実際の導入は、2026 年度以降からという見方が濃厚である。
最後に
.jpg)
こどもNISAが生まれ、商品も増え、スイッチングで自由度も広がる。
制度はどんどん進化しているね。
でも、本当に大事なのは「制度がどうこうではなくて、自分の軸(投資行動)が一本しっかりとしているかどうか」。
未来をよくするのは、制度じゃなく、あなたの“行動”なんだ。
今回は、「最新版NISAの改正案」について解説していきました。
今回の改正案が実現した際は、ぜひあなた自身の投資行動を見直し、確立するきっかけにしてくださいね。
このブログでは、しっかりとした調査研究のもと、正確な情報発信ができるよう努めて参ります。よかったらまたいらっしゃってください。
.jpg)
信じて、託そう。未来の自分に!
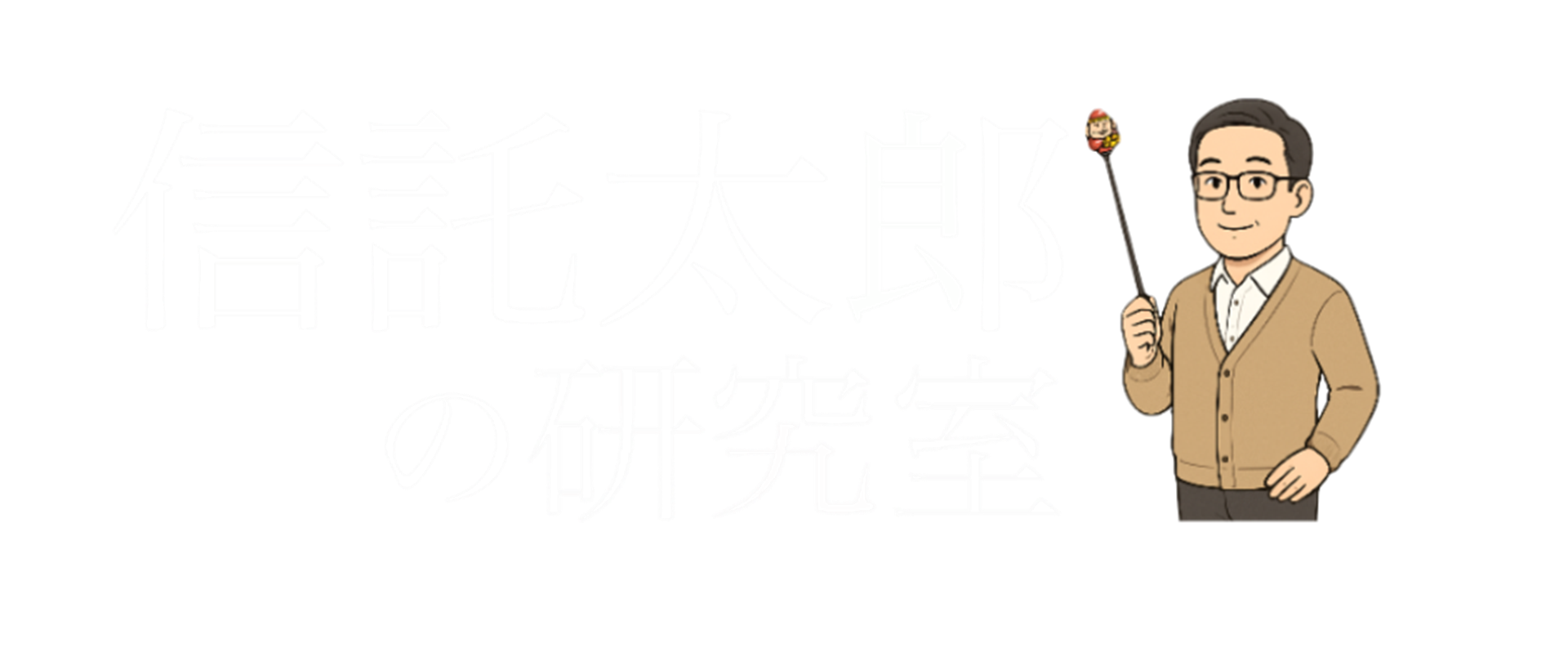
-150x150.jpg)